
大体のことがオンラインで済み、コロナ禍がその追い風となった今。人や物、電波などから距離を置き「オフ」の時間をあえて作り、音を楽しむという価値を考えるキャンペーンがスタート!アンビエント、ニューエイジ、ポスト・クラシカル、ホーム・リスニング向けの新譜や旧譜を、写真家:津田直の写真や音楽ライター・識者による案内を交えながらご紹介。
 “Tranquility at the Shore #20” © Nao Tsuda, Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film
“Tranquility at the Shore #20” © Nao Tsuda, Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film
新型コロナウイルスの蔓延により、音楽の現場が自粛を余儀なくされた時、筆者がまっさきに連想したのは、夏フェスはどうなるのか?ということだった。そして、ほぼ予想通り(残念なことに)ロック・イン・ジャパン、フジロックなどが早々に中止を宣言した。
筆者が思うフェスのいいところは、観客が高揚感や一体感に浸れるところ。だから、フェスでウケるバンドの音楽性にはには一定の傾向がある。彼らは規則的なビート(特に4つ打ち)の反復や一緒に口ずさめるサビをライヴ向けに用意し、両者が同じ振付をしたりもする。要するに、インタラクティヴなやりとりにより、バンドとリスナーの両者の壁が取り払われたということだ。だからこそ、CDの売り上げが落ちる一方で、ライヴやフェスへの動員は増えていたのだろう。
だが逆に、大人数の他者と悦びを分かちあうのではなく、部屋でひとりで、時に孤独にひたりながら聴くべき音楽もある。アンビエント/ニューエイジ/ポストクラシカル/ホームリスニングなどと呼ばれる音楽がそれにあたる。そうした作品はフェス受けするような先述の要素こそ欠いているが、いや、欠いているからこそ、普段CDを買わない人にとっては異なる快楽が訪れる。ライナーノーツやアートワークを眺めながら、集中して音源に向き合う時間はそうそうないというリスナーにこそ、今は1対1で音源に浸ってほしい。
私事だが、筆者が10年程前に心身の不調により、自宅にこもっていた時に聴いていたのは、アンビエントの創始者であるブライアン・イーノやエリック・サティだった。それらは聴きこむことも聞き流せることもできるものであり、ネットサーフや仕事のBGMとして最適だった。それらには心の揺れを静めてくれるような響きがあった。
また昨今、シティ・ポップに続いて、日本の80年代の環境音楽を見直そうという動きが、海外のリスナーから出てきている。実際、米国のライト・イン・ジ・アティックというレーベルからリリースされたコンピレーションがそうしたムーヴメントをまとめ、吉村弘、高田みどり、芦川聡などの80年代の環境音楽を発掘/再発見しており、それらのディスクは、今なお新鮮な響きを失っていない。
筆者は芦川聡を批評家・佐々木敦の著作『テクノイズ・マテリアリズム』でかなり前に聴いていたし、東京藝大で角銅真実の教師だった芦川も愛聴していた。ただ、彼らの音源はストリーミング・サーヴィスにはほぼないので、これを機にフィジカルに傾聴するのもいいのではないか。共感/共有の音楽から、個人で没入する音楽。そうしたものが、コロナ禍の今、切実に求められるのではないだろうか。
土佐有明
筆者が思うフェスのいいところは、観客が高揚感や一体感に浸れるところ。だから、フェスでウケるバンドの音楽性にはには一定の傾向がある。彼らは規則的なビート(特に4つ打ち)の反復や一緒に口ずさめるサビをライヴ向けに用意し、両者が同じ振付をしたりもする。要するに、インタラクティヴなやりとりにより、バンドとリスナーの両者の壁が取り払われたということだ。だからこそ、CDの売り上げが落ちる一方で、ライヴやフェスへの動員は増えていたのだろう。
だが逆に、大人数の他者と悦びを分かちあうのではなく、部屋でひとりで、時に孤独にひたりながら聴くべき音楽もある。アンビエント/ニューエイジ/ポストクラシカル/ホームリスニングなどと呼ばれる音楽がそれにあたる。そうした作品はフェス受けするような先述の要素こそ欠いているが、いや、欠いているからこそ、普段CDを買わない人にとっては異なる快楽が訪れる。ライナーノーツやアートワークを眺めながら、集中して音源に向き合う時間はそうそうないというリスナーにこそ、今は1対1で音源に浸ってほしい。
私事だが、筆者が10年程前に心身の不調により、自宅にこもっていた時に聴いていたのは、アンビエントの創始者であるブライアン・イーノやエリック・サティだった。それらは聴きこむことも聞き流せることもできるものであり、ネットサーフや仕事のBGMとして最適だった。それらには心の揺れを静めてくれるような響きがあった。
また昨今、シティ・ポップに続いて、日本の80年代の環境音楽を見直そうという動きが、海外のリスナーから出てきている。実際、米国のライト・イン・ジ・アティックというレーベルからリリースされたコンピレーションがそうしたムーヴメントをまとめ、吉村弘、高田みどり、芦川聡などの80年代の環境音楽を発掘/再発見しており、それらのディスクは、今なお新鮮な響きを失っていない。
筆者は芦川聡を批評家・佐々木敦の著作『テクノイズ・マテリアリズム』でかなり前に聴いていたし、東京藝大で角銅真実の教師だった芦川も愛聴していた。ただ、彼らの音源はストリーミング・サーヴィスにはほぼないので、これを機にフィジカルに傾聴するのもいいのではないか。共感/共有の音楽から、個人で没入する音楽。そうしたものが、コロナ禍の今、切実に求められるのではないだろうか。
土佐有明
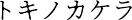
− 津田直(写真家)
二年前の初夏、僕はフィンランド南西部のアーキペラゴ(群島)を旅していた。友人で写真家のリトヴァ・コヴァライネンの家でランチをしながら、「長い冬を乗り越え、夏の訪れを告げる瞬間。木の葉が開くような、夏の始まりに立ち会いたいくて…」と彼女と話していたら、「ならば島の人に伝えておくから、ヴァーノ島へ行くといいわ」と送り出してくれた。
港に車を預け、船に乗り、群島の隙間を抜けるように水を分けながら、風景に入っていく。向かった島の人口は、たったの15人だという。フィンランドや北欧の人々は夏の過ごし方のひとつとして、サマーハウスで…という人が多い。サマーハウスとは、いわゆる別荘と呼ばれる類の贅沢なつくりの家とは違って、忙しい日常を離れて、森や湖のそばで自然の声に耳を傾けるように建てられている簡素な小屋のことをいう。家庭にもよるけれど、電気や水道すら通していない場合も多く、必要最小限の物だけを持ち込み、つつましく自然に寄り添う人々たちの夏。まさにそこには、オフノオトがあった。朝日と共に目を覚まし、白夜の蒼い光の中に一日を終える日々。これまでの人生で、空をゆく白鳥の羽音がこんなにも大きく聴こえたり、歩きながら頭の中に描いた地図を頼りに一日歩きまわったり、一夜をこんなにも長く感じたりしたことがあっただろうか。あの夏に経験した時の流れは、この星の元来の姿なのかもしれないと気がついた。
僕らはコロナ禍を通じて、今一度帰るべきところに向かい始めているのかもしれない。少なくとも、僕らはオフの時間の中に、忘れかけていた時の欠けらを見つけたはずだ。僕は未来をここから、想像していきたいと思っている。
 “Tranquility at the Shore #4” © Nao Tsuda, Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film
“Tranquility at the Shore #4” © Nao Tsuda, Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film
“Tranquility at the Shore #14” © Nao Tsuda, Courtesy of Taka Ishii Gallery Photography / Film
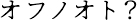
− 青野賢一
大体のことはオンラインで足りる。便利な世の中になったものであるが、たとえばSNSやショッピング、あるいは何かの手続きのように、オンラインの状態というのは必ず対象が存在するわけで、一方的かインタラクティブかの別はあるにせよ対象とのやりとりが生じる。これが続くと、思いがけず時間をとられてくたびれたりはしないだろうか。何らかの便利さと引き換えに別の時間が削られ、また疲弊させられるのは、インターネット時代に特有の事象かもしれない。さて、そんなやりとりに疲れた時には、自ら進んでオフ状態を作るのがいいだろう。そして、オフ状態のお供には想像力を刺激する上質な音楽をぜひ。リラックスして楽曲に心と体を預ければ、便利さに侵食された自己を取り戻すことができるはずである。その点、今回ご紹介する3作品なら間違いない。
 Bing & Ruth - Species
Bing & Ruth - Species2015年の『City Lake』、2017年の『No Home Of The Mind』と、ピアノを基調としたコンテンポラリーな音楽と丁寧にプロセッシングされた電子音を巧みに融合したユニークな作品を展開してきたBing & Ruth(ビング・アンド・ルース)。ブルックリン・ベースのピアニストでコンポーザーのデヴィッド・ムーアを中心としたこの不定形室内音響アンサンブル・プロジェクトの最新作『Species』は、スライ・ストーンやピンク・フロイドのリチャード・ライトが愛用したことでも知られるイタリアの電子オルガン〈Farfisa(ファルフィッサ)〉を全面にフィーチャーしたもの。テリー・ライリーを彷彿させるミニマルな楽曲群は、微風が砂漠の表面を撫でて少しずつ表情を形づくってゆくような、ゆっくりと移り変わるおおらかなフィジカルさが実に心地よい。
 Julianna Barwick - Healing Is A Miracle
Julianna Barwick - Healing Is A Miracleニューヨークで活動していたジュリアナ・バーウィックが2019年春にロサンゼルスへと拠点を移して制作した『Healing Is A Miracle』。幽玄なボイスと繊細なエレクトロニクスが紡ぐバーウィックの世界はそのままに、ゲスト参加したハープ奏者のメアリー・ラティモア、シガー・ロスのヨンシー、プロデューサーでDJのノサッジ・シングがそれぞれの持ち味を存分に発揮してアルバムに彩りを添えている。本作のタイトルは、バーウィックが人間の自然治癒力に改めて感嘆し、その作用を奇跡のようなことと捉えたところから付けられたというが、なるほど一つ一つの音が細胞レベルに響きわたるような浸透度の高い仕上がりである。そうして聴く者の内面に入り込みつつも、そこに留まらないで循環してゆく抜けのよさ、ある種の浄化的な効果も特筆すべき点だろう。
 原 摩利彦 - Passion
原 摩利彦 - Passion約3年ぶりとなる原摩利彦のオリジナル・アルバム『Passion』は、これまでの原の活動の集大成であり、同時に新たなアプローチも随所に取り入れた意欲作だ。リリカルでイマジネーション豊かなピアノの旋律と、自身で収集したフィールドレコーディング素材を緻密に音楽に仕立ててゆく従来のスタイルに加え、他者の録音によるフィールドレコーディング素材を用い、また非西洋圏である中東の楽器を、本人の言葉を借りれば「『音響的』に共存させる」取り組みにより、これまでになくバリエーション豊かな作品が完成した。イタリア、インド、メキシコ、フランスでそれぞれ録られたフィールドレコーディング素材は、直接的にその場所を指し示しはしないが、楽曲の温度に大きく作用しているといえるだろう。そんなところからか、聴くと様々な色が脳裏に浮かぶ。

− 大西穣
アロマを炊くように、そっと流しておけば良い。初めから終わりまで通して聴く律儀な作法は無用だ。いつの間に部屋を瞑想的な空気で満たし、聴く者をどこか異世界へと連れ出してくれるだろう。ニューエイジやアンビエントと呼称されるそんな音楽は、昨今のホームリスニングの中で昨今、再び脚光を浴びている。ここに挙げる作品は、ブライアン・イーノと彼と馴染みの深いジョン・ハッセル、ララージの新旧6作品。1977年の作品から最新作までのいずれの作品にも、時代を先駆けてきたオリジネイターによる、決して古びることのない「深さ」がある。それに遭遇すると、じっくりと味わいたくもなる。表層的な、あるいは深層的なリスニング両者に対応されて作られ、様式的にも自在的にも過去と現在を行き来しやすいのもこのジャンルの魅力と言えるだろう。
 Jon Hassell - Vernal Equinox (1977)
Jon Hassell - Vernal Equinox (1977)イーノは一回り近く年上のハッセルからの恩恵を公言し、称賛する。ハッセルが凄まじいのは、現代音楽のシュトックハウゼンに師事、ミニマルミュージックのラ・モンテ・ヤングの演奏集団のメンバーで、さらにインド音楽のプラン・ナートからラーガを学ぶ、といった具合だ。当時の先端的な音楽を貪欲に吸収したのちに、ほとんど単独突破のような形で「第4世界」の音世界を作り上げてしまった 。エレクトリック・マイルスからの影響を受け、シンセサイザーが珍しい時代に、電子音楽のパイオニア、デヴィッド・ローゼンブームのスタジオで録音。さらにブラジリアンの打楽器奏者、ナナ・ヴァスコンセロスらの参加が独自の音世界を作る。異世界を感じさせ、のちのアンビエントに絶大な影響を与えた、類を見ない到達地点。
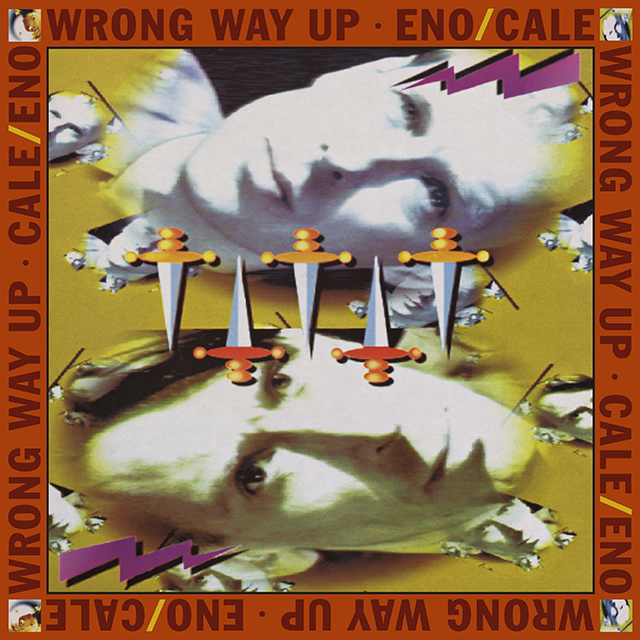 Brian Eno & John Cale - Wrong Way Up (1990)
Brian Eno & John Cale - Wrong Way Up (1990)リイシュー作品のもう片方で、70年代から交流が深かったイーノと、exヴェルヴェット・アンダーグラウンドのジョン・ケイル両者が、再び共作したのが90年の今作品。イーノも歌手として参加、数曲はデュエットまで披露している。80年代をほぼインストのアンビエントアルバムを作っていたイーノが再びポップアルバムを作る意思を固めたのは衝撃だったが、両者の力の拮抗が奇跡的なポップスを生み出した。音楽面では、ゴスペルやアラブ音楽、それにドゥーワップからの影響を感じさせ、またイーノの声質も低音に伸びが見られ、成熟した表情を湛えている。イーノの他のアンビエント作品のように非常に抑制されたプロダクションにナンセンスな色合いの強い歌詞に落ち着いた上品なヴォーカルが乗る。両者にとってもそれぞれの最上位に位置する傑作である。
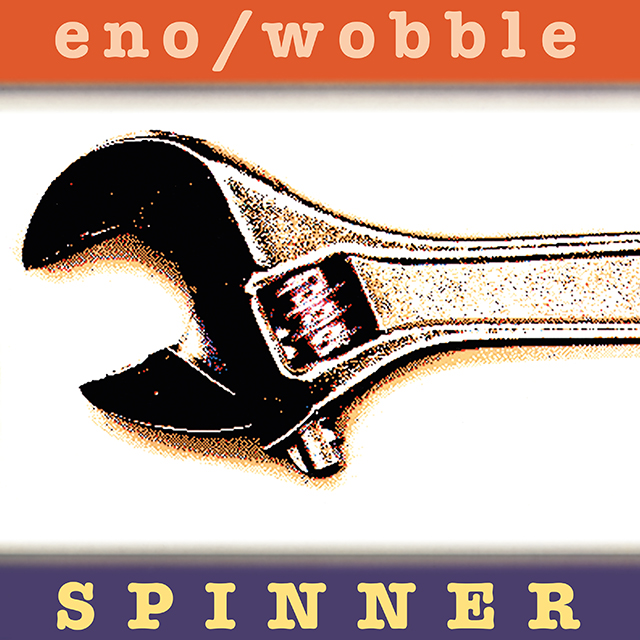 Brian Eno & Jah Wobble - Spinner (1995)
Brian Eno & Jah Wobble - Spinner (1995)兄弟名義の作品を初めてリリースするなど話題を欠くことのないイーノの、リイシューされた過去のコラボ2作品のうちの1つ。元々は実験映画作家デレク・ジャーマン作品のサウンドトラックとして作られた。イーノ作品特有の引き伸ばされたシンセ音が、どこか歪んだ時空間を演出するのだが、パブリック・イメージ・リミテッドのジャー・ウォブルがダブ的なベースを、控えめに演奏する。相反する2人の音楽世界が音楽的に調和するのではなく、対峙しあう。さらにジャーマンロックCANのドラマー、ヤキ・リーベツァイトがタイトル曲を含め後半の数曲に参加し強烈なリズム隊のグルーヴを作る。それに対して、どこかサティを思わせるような優雅な、しかし不穏な旋律がまとわりつく。肉感的な演奏にクールな視点が光る、不思議な魅力を持つアルバムだ。
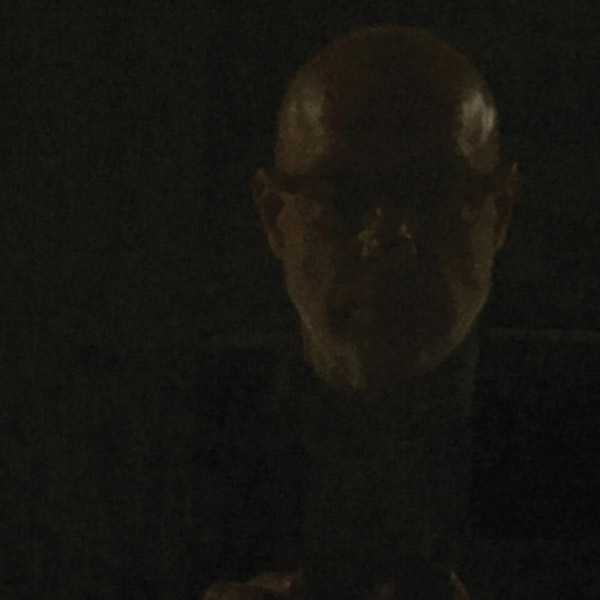 Brian Eno - Reflection (2017)
Brian Eno - Reflection (2017)電子音のドローンが一音立ち現るとゆっくりと減衰していく。時折、まるでフレーズらしきものが出現したり、低音や高音部が重なり合う。しかし特に発展はなく、やがてまた消えていく。しかし54分間には、耳をすませていると瞑想的な美と形容したくなる瞬間がある。省察、あるいは熟考という意味の“Reflection”は、まさに音楽という他者との対話であり、あるいはその変化に対する自己の感情への省察でもある。音楽の中で意志やエゴを取り払い、ディスクリート(控えめな)ミュージックという、アンビエントの持つ中心的な側面をジェネレイティヴ(自動生成的)な作曲のシステムを構築し作動させている。川のほとりで常に変化する水の流れを見ているような、アンビエント的美学の最も洗練された形と言えるだろう。
 Laraaji - Sun Piano (2020)
Laraaji - Sun Piano (2020)ララージはニューエイジ・アンビエントのレジェンドにしてエレクトロニック・ツィター奏者。1978年NYのワシントン・スクエアで大道芸的なパフォーマンスをしていたところ、偶然通りかかったイーノと遭遇し、名作『Day of Radiance』へとつながった逸話は有名だ。そんな彼が原点であるピアノの作品を作った。豪快なタッチと安定感抜群のリズム感に支えられ、てらいがなく、そして深い。彼の中では、ハワード大学で作曲を専攻していた頃からスタンドアップ・コメディアンへの道も考えていたように、音楽とは切り離すことができない“笑い”が見られる。“笑い”がもたらす心理的な恩恵、実はそれこそがアンビエントにも彼が貢献していた要素なのだが、生涯追及してきたエッセンスが、このアルバムにはふんだんに味わえる。
 Jon Hassell - Seeing Through Sound (Pentimento Volume Two) (2020)
Jon Hassell - Seeing Through Sound (Pentimento Volume Two) (2020)自身の提唱した「第4世界」は、常にアップデートしなくてはクリシェに陥りマンネリ化する。色の塗り重ねにより、見えなくなっていた元の画像や描写、表現が再び見えることを意味する“Pertimento”をシリーズのタイトルにつけたように、テクノロジーのアップデートを含めた表現で、『Vernal Equinox』以降の自分と対峙している。80を越えたら流石に電子音楽に対する感受性は落ちるだろうと邪推したが、〈WARP〉の傘下の自己レーベル〈Ndeya〉から出されており、電子音楽色はむしろ強まり、「Unknown Wish」や「Reykyavik」「Timeless」の妥協のない再構築のクリエイティヴィティは光るものがある。個人的には多層的な音響の中に現れる、エレクトリックマイルスを彷彿させるキーボードワークが嬉しい。
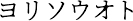
− 田中雄大
配信や動画サイトの発達によって、かつてないほど音楽が溢れている昨今。たしかにメリットは多い。リスナーはスマートフォン1台で古今東西の音楽に触れられるし、音楽家にとっても発信が容易になった。ただ一方で、次々と現れる音楽たちはどれも、自分の横を素通りしていくような気がしてならない。その途中、少し引っかかることはあっても、深く関わり合う間柄にはならないのだ。日常や生活に寄り添う、そんな音楽を見つけるには、もっと丁寧なやりとりが必要なのだと思う。例えばお気に入りの家具や腕時計。こういったモノとの間には、出会った瞬間から今までの物語があるはずだ。それと同じように、じっくりと作品に向き合い、耳を傾け、自分と重ね合わせる。そうした一歩の先にこそ、心に寄り添う素敵な音楽との出会いが待っているのではないか。
 Bruno Major - To Let A Good Thing Die
Bruno Major - To Let A Good Thing Dieブルーノ・メジャーの音楽は非常に視覚的だ。色褪せたフィルムのような淡い心地良さが全体に漂い、その上で歌うのは日常の何気ない風景。例えば本作の「I'll Sleep When I'm Older」で描かれるのはパリの春やタバコを吸っている場面で、その着飾らない姿には誰もが親近感を抱く。ロンドンの北、ノースハンプトン出身のブルーノは幼少期からクラシック音楽を学び、のちにジョー・パスを始めとするジャズ・ギターへ傾倒するという経歴の持ち主。中でも特に30年代〜40年代頃のアメリカン・ソングブック、加えてジャズ・スタンダードからの影響が大きく、前述した“古き良き”音世界はそうしたルーツから生まれてくるもの。移動のBGMにするのではなく、部屋でゆっくりと、映画を観るように聴きたい作品だ。
 Bibio - Sleep On The Wing
Bibio - Sleep On The Wingアンビエント系の出自を持ちつつ、フォークやインディー・ロック、テクノまで多様な音楽性を自在に操るビビオことスティーヴン・ウィルキンソン。今作は60年代から70年代頃のフォーク・ミュージックを強く意識した2019年のアルバム、『Ribbons』の延長線上に位置するEPだ。繊細で巧みなアコースティック・ギターと美しいストリングスで描かれる空間は、豊かな自然の息吹を感じさせつつも、同時にこの世のどこでもない、まるで夢の中のような浮遊感も持ち合わせる。ビビオの作品はどれもノスタルジーを感じさせるが、今作のそれは特に強いように思う。おそらく、世界中の誰が聴いてもそれぞれの“懐かしさ”に立ち返ることができる。世間の喧騒を忘れて自分の内面と向き合う、そんな贅沢な時間を生み出してくれる1枚である。
 Tom Misch - Beat Tape 1
Tom Misch - Beat Tape 1稀代のビートメイカーでありギタリスト、トム・ミッシュによる初めてのセルフ・リリース作品で、当時19歳にして作曲から演奏、ミックス/マスタリングまでを自身で手がけた1枚。トム・ミッシュの革新性は、多くのアーティストが模索した“ビート・ミュージックとギターの融合”というテーマに対して、驚くほどスマートな解答を提示したことだ。その要因は、本作に「Dilla Love」という楽曲を収録するほどJ・ディラを敬愛しつつ、ギター面でのヒーローはジョン・メイヤーという、彼以前の世代では交わることのなかった音楽性の自然なハイブリッド感覚。2018年の傑作『Geography』はそうした才能が完全に開花したことを世界に示すものだったが、この『Beat Tape 1』にもその片鱗は見えている。
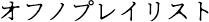
 牛尾憲輔(agraph)のオフノオト
牛尾憲輔(agraph)のオフノオト自宅でオフの機会、増えましたね。 なんだかもう音楽を聴いているのか、生活しているのか、だらだらしているのか寝ているのか起きているのかよくわかりません。
ベッドで横になったまま、体は全く動きません。
2008年にソロユニット"agraph"としてデビュー。その後LAMAのメンバーとしても活動。電気グルーヴをはじめ、様々なアーティストの制作、ライブをサポート。アニメ「ピンポン」の劇伴を担当したのをきっかけにアニメ、劇場映画の劇伴も多数手がける。REMIX、プロデュースワークをはじめ、CM音楽を手掛けるなど多岐にわたる活動を行っている。
 原 摩利彦のオフノオト
原 摩利彦のオフノオトずっと家で過ごしていると「オン/オフ」の境界はどんどん曖昧になってしまう。体と頭を休めて好きなことだけをする「オフ」の時間。それでまた明日からも前に進んでいける。「オフ」をより豊かに過ごせるための音楽。僕にとっては模様替えをする時のための音楽です。
音楽家。1983年生まれ。京都大学教育学部卒業。同大学大学院教育学研究科修士課程中退。 親しみやすいピアノ曲から先鋭的な音響作品まで、舞台・現代アート・映画など、さまざまな媒体形式で制作活動を行い、坂本龍一、野田秀樹といった第一線で活躍するアーティストとのコラボレーション・プロジェクトなど、幅広く活動。
 「オフノオト」まとめプレイリスト
「オフノオト」まとめプレイリスト本冊子で紹介されている作品に収録された楽曲にアクセスできるプレイリストが公開中。
Bing & Ruth x 原 摩利彦による交換日記がThem Magazineでスタート。
#1 「はじめまして。最近、どんな風に過ごしていた?」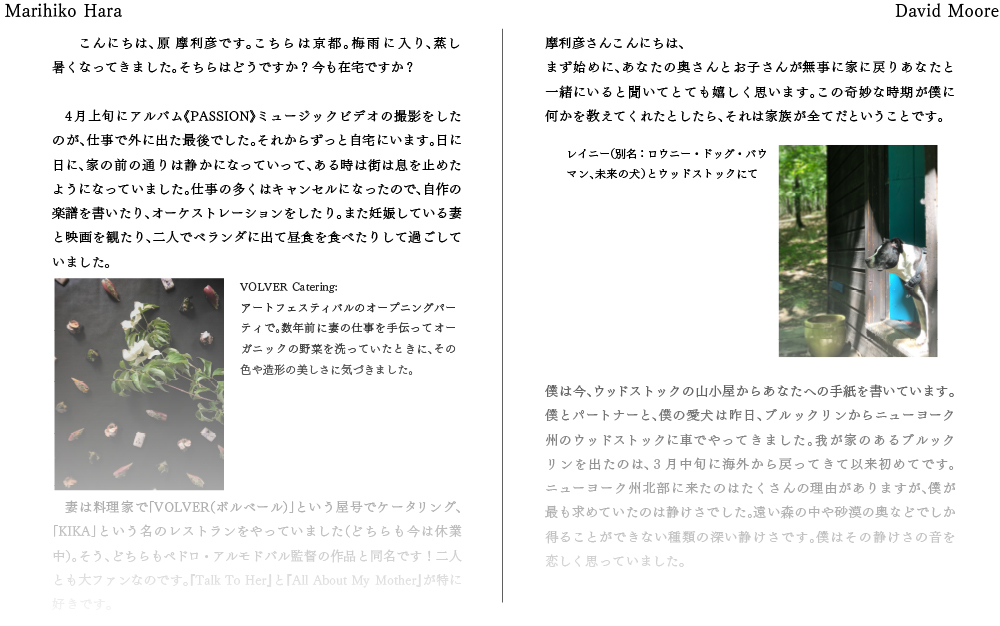
続きはThem MagazineのWebサイトで公開!(7/22公開)
表紙・掲載写真

テキスト
土佐有明
ライター。明治大学文学部卒業後、『ミュージック・マガジン』、『クイック・ジャパン』などで音楽について執筆を開始。現在は書評や演劇評も手掛けている。
最近書いたのは金原ひとみ論(『リアルサウンドブック』)と坂本真綾論(『ミュージック・マガジン増刊』)。大森靖子が好き。
青野賢一
個人のリソースを主に社外のクライアントワークに生かす「ビームス創造研究所」のクリエイティブディレクター兼〈BEAMS RECORDS〉ディレクター。
1987年よりDJ、選曲家活動を開始し、現在は都内のクラブやミュージックバーを中心にプレイ。
また、音楽、映画、文学、美術、ファッションなどをジャンル横断的に論ずるライターとして、『CREA』『ミセス』『音楽ナタリー』などに連載を持つ。
大西穣
東京生まれ。バークリー音楽大学卒。ボストンやNYCの実験音楽シーンで活動。
帰国後は音楽制作会社にてCM音楽制作やBGM選曲など国内外の様々なプロジェクトに従事。佐々木敦と東浩紀が主催するゲンロン批評再生塾を修了後、執筆活動を開始。訳書にジョン・ケージ『作曲家の告白』(アルテスパブリッシング)などがある。
田中雄大 / ギター・マガジン編集部
1991年生まれ、愛知県出身。2015年にリットーミュージックへ入社。
以降、ギター・マガジン編集部にて特集「ネオソウル・ギターとは?(2019年10月号)」、「チューブスクリーマー40年史(2019年6月号)」など、数々の企画/編集を担当。2018年にはトム・ミッシュの対面インタビューも実施した。

津田直
写真家。1976年神戸生まれ。世界を旅し、ファインダーを通して古代より綿々と続く、人と自然との関わりを翻訳し続けている。文化の古層が我々に示唆する世界を見出すため、見えない時間に目を向ける。2001年より多数の展覧会を中心に活動。 2010年、芸術選奨新人賞美術部門受賞。
主な作品集に『SMOKE LINE』、『Storm Last Night』(共に赤々舎)、『SAMELAND』(limArt)、『Elnias Forest』(handpicked)がある。 https://tsudanao.com
写真家。1976年神戸生まれ。世界を旅し、ファインダーを通して古代より綿々と続く、人と自然との関わりを翻訳し続けている。文化の古層が我々に示唆する世界を見出すため、見えない時間に目を向ける。2001年より多数の展覧会を中心に活動。 2010年、芸術選奨新人賞美術部門受賞。
主な作品集に『SMOKE LINE』、『Storm Last Night』(共に赤々舎)、『SAMELAND』(limArt)、『Elnias Forest』(handpicked)がある。 https://tsudanao.com
テキスト
土佐有明
ライター。明治大学文学部卒業後、『ミュージック・マガジン』、『クイック・ジャパン』などで音楽について執筆を開始。現在は書評や演劇評も手掛けている。
最近書いたのは金原ひとみ論(『リアルサウンドブック』)と坂本真綾論(『ミュージック・マガジン増刊』)。大森靖子が好き。
青野賢一
個人のリソースを主に社外のクライアントワークに生かす「ビームス創造研究所」のクリエイティブディレクター兼〈BEAMS RECORDS〉ディレクター。
1987年よりDJ、選曲家活動を開始し、現在は都内のクラブやミュージックバーを中心にプレイ。
また、音楽、映画、文学、美術、ファッションなどをジャンル横断的に論ずるライターとして、『CREA』『ミセス』『音楽ナタリー』などに連載を持つ。
大西穣
東京生まれ。バークリー音楽大学卒。ボストンやNYCの実験音楽シーンで活動。
帰国後は音楽制作会社にてCM音楽制作やBGM選曲など国内外の様々なプロジェクトに従事。佐々木敦と東浩紀が主催するゲンロン批評再生塾を修了後、執筆活動を開始。訳書にジョン・ケージ『作曲家の告白』(アルテスパブリッシング)などがある。
田中雄大 / ギター・マガジン編集部
1991年生まれ、愛知県出身。2015年にリットーミュージックへ入社。
以降、ギター・マガジン編集部にて特集「ネオソウル・ギターとは?(2019年10月号)」、「チューブスクリーマー40年史(2019年6月号)」など、数々の企画/編集を担当。2018年にはトム・ミッシュの対面インタビューも実施した。